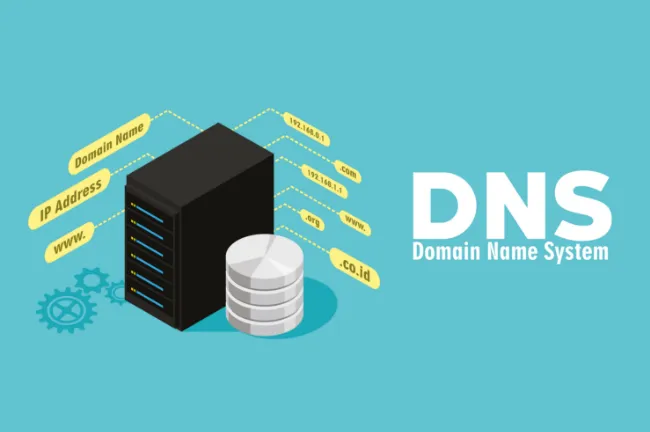保守管理会社を変更する際のドメイン移管のタイミング
目次
はじめに
ホームページの保守管理を他の業者に依頼したいと考えたとき、避けて通れないのが「ドメイン移管」の問題です。特に現在の保守管理会社がドメインの取得や更新、DNS設定までを一手に担っていた場合、その移管には細心の注意が必要です。タイミングを誤ると、ホームページが一時的に表示されなくなったり、メールが届かなくなるといった深刻なトラブルにつながることもあります。
このコラムでは、保守管理会社を変更する際にドメイン移管のタイミングをどう見極め、どのような準備をして進めるべきかを、実際の運用に即して解説します。
なぜドメイン移管が必要なのか?
そもそも、保守管理会社を変える際に「ドメイン移管」が必要になるのはなぜなのでしょうか。ドメインは、ホームページのURLやメールアドレスの一部として使用される重要な資産です。
たとえば、現在の保守会社がドメインの新規取得から契約更新、ネームサーバー(DNS)の設定、所有者情報の管理、さらにはSSL証明書の発行までを一括で担っている場合、保守管理の変更とともにドメインの管理体制も見直す必要があります。このような体制のままでは、変更後も旧管理会社に依存し続けることになり、今後のトラブル対応や運用に支障が出るリスクが残ります。
そのため、ドメインも新しい保守管理会社、あるいは自社が直接管理できる体制へと移管することが推奨されます。これにより、技術的にも運用面でも一貫性を保ち、安心してサイト運用を続けることが可能になります。
ドメイン移管の基本的な流れ
ドメイン移管とは、現在契約しているドメイン登録業者(レジストラ)から別の登録業者へとドメインの管理権限を引き継ぐことです。
まず最初に、現在のドメイン管理者から「AuthCode(オースコード)」と呼ばれる認証コードを取得します。これは移管に必要な鍵のようなもので、所有権確認のために求められます。続いて、ドメインロックと呼ばれる移管防止設定を解除し、新しいドメイン管理会社で移管申請を行います。
移管申請が通ると、ドメイン所有者に対して承認メールが送られ、これに応じることで移管が正式に進行します。その後、DNS設定やWhois情報の変更、SSL証明書の再発行などを新しい環境で行い、最終的にホームページやメールの動作確認を実施します。
この一連の作業は、ドメインの種類によっても所要時間が異なり、一般的に数日から2週間ほどかかる場合があります。
ドメイン移管におけるタイミングの重要性
ドメイン移管をスムーズに行うには、適切なタイミングでの実行が何より重要です。タイミングを誤ると、たとえばホームページが一時的に表示されなくなったり、メールの送受信ができなくなるといった問題が起こり得ます。さらには、検索エンジンの評価に影響が出たり、管理者権限の引き継ぎが曖昧なまま終わってしまうなど、予期しないトラブルを招くこともあります。
このような事態を防ぐには、移管作業をいつ行うか、どの段階で準備を整えるかを慎重に見極める必要があります。
契約更新日前の2〜3ヶ月前から準備を始める
ドメイン移管を検討する際に最も基本となるのが、契約更新日の2〜3ヶ月前から移管準備を始めるという点です。ドメイン移管には思いのほか時間がかかるため、早めの行動が重要です。
実際にレジストラによっては、有効期限の30日以内には移管申請を受け付けないという規定を設けている場合もあり、間際に動き始めると移管ができず、やむを得ず旧業者での契約を更新することになります。そうなると、変更の計画がずれ込み、再度日程を見直さなければならなくなるため、少なくとも2ヶ月前には新旧管理会社間での段取りを整え、スムーズな引き継ぎができるようにしましょう。
ホームページのリニューアルと同時に移管を行う
保守会社の変更は、ホームページのリニューアルやサーバーの切替と併せて行うことが多いため、この機会にドメインの移管も同時に行うと効率的です。
リニューアルに伴って新しいサーバー環境を構築する場合、その設定に合わせてDNSやSSL証明書も再設定が必要になることが一般的です。ドメインの移管を同時に行えば、これらの設定作業を一元化できるため、ミスも減り、結果的にコストと手間を抑えられることにもつながります。
メールの移行計画と連動させる
ドメインに紐づくメールアドレスを使っている場合、ドメイン移管と同時にメールサーバーの切替も行う必要があります。この時に十分な準備がないと、メールが送受信できない状態に陥ることがあります。
たとえば、MXレコード(メールの配送先を示す設定)の切替は、DNS設定が反映されるまでに数時間から長ければ1日程度かかることもあります。その間にメールが宙に浮いてしまい、重要な連絡が届かないというトラブルが起きる可能性があります。
したがって、メールの移行計画をしっかり立てたうえで、必要な設定がすべて整ったタイミングでドメイン移管を行うべきです。
ドメインの凍結期間(60日ルール)に注意する
ドメインには「取得から60日以内は移管できない」という国際的なルールがあります。これはICANNという組織によって定められており、ドメインの不正な売買や乗っ取りを防ぐためのものです。
また、Whois情報(ドメインの登録者情報)を変更した場合にも、この60日間の凍結ルールが適用される場合があります。したがって、保守会社を変更する直前にWhois情報を修正すると、思わぬタイミングで移管ができなくなることもあるため、事前に登録情報の状態を確認しておくことが大切です。
実際の進行スケジュール例
たとえば、保守会社の変更とドメイン移管を計画的に行う場合、3ヶ月ほど前から準備を始めるのが理想的です。最初のステップとして、現在の契約内容を見直し、ドメインの管理者が誰であるか、更新期限がいつか、Whois情報に誤りがないかを確認します。
次に、2ヶ月前には新しい保守会社との契約を締結し、新サーバーや新しいメール環境の構築を依頼します。DNSやSSL証明書に関する要件もここで整理しておくと良いでしょう。
そして、1ヶ月前にはAuthCodeの取得、ドメインロックの解除、移管申請の準備などを行い、具体的な移管手続きをスタートさせます。その後、3週間前には正式な申請を行い、移管完了を待つとともに、ネームサーバーやDNSの切替準備を進めます。
2週間前には実際のDNS設定変更、SSL証明書の発行、メールの受信確認などを行い、サイト表示やメールの動作確認が取れた段階で、1週間前には旧サーバーや旧保守体制との完全な切り離しを行い、移管プロジェクトを完了させます。
トラブル事例と教訓
現場では「旧保守会社からAuthCodeがなかなかもらえなかった」「Whois情報が旧業者名義で移管できなかった」「DNS切替後にメールが届かなくなった」など、実際に起きがちなトラブルが多数あります。
このような問題の多くは、事前の確認不足や、旧業者との連携の不備によって起こります。あらかじめ丁寧な段取りを組み、情報の所有者をはっきりさせてから作業を進めることが、トラブル回避のための最善策となります。
ドメインは「会社の財産」、主体的な管理を意識する
ドメインは単なる「ホームページのアドレス」ではなく、会社の信用やブランドイメージを形づくる重要な資産です。その管理を他人任せにしてしまうと、いざという時に手が出せず、大きな損失につながるおそれがあります。
だからこそ、保守会社の変更を機に、ドメイン管理を自社で主体的に行う体制を整えることが望まれます。仮に外部に委託する場合でも、所有者情報や契約更新の権限は自社が保有している状態が理想です。
まとめ
焦らず、準備を怠らず、正しいタイミングで進めよう
保守管理会社の変更は大きな節目であり、ドメイン移管はその中心となる重要な作業です。これを安全に進めるためには、焦らず十分な準備期間を取り、関係者との連携を密にして、適切なタイミングで実施することが鍵となります。
とくに、契約更新日から逆算して2〜3ヶ月前には準備を開始し、メールやホームページといった関連機能の動作確認もあわせて行う体制を整えることが、成功への近道です。
このコラムを書いた人

さぽたん
ホームページに関するお困りごと、
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください!