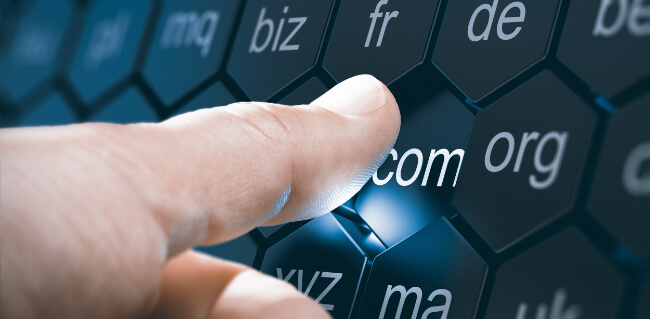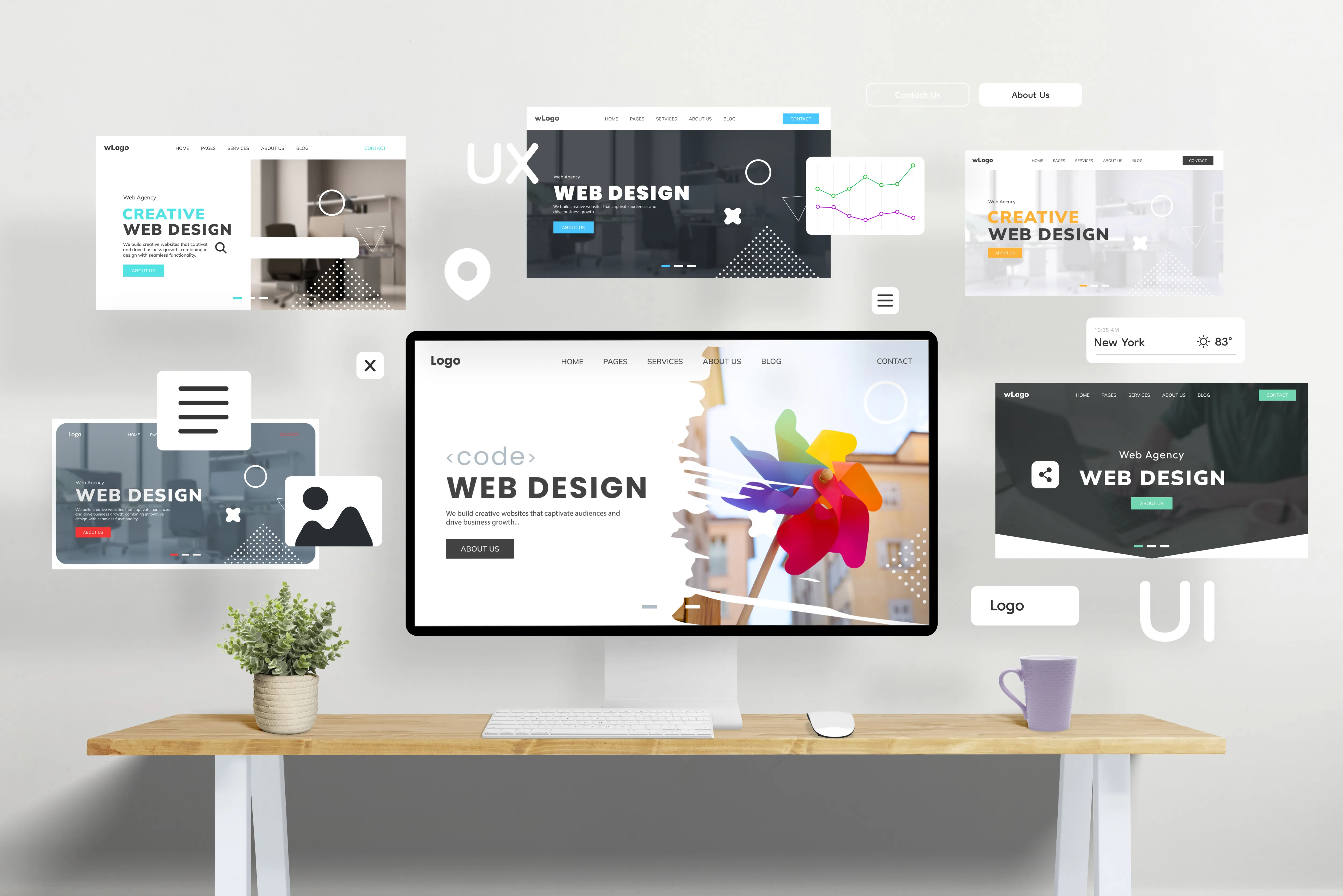ホームページがないと公的な申請ができない!?最近のホームページの存在意義
目次
はじめに
かつてホームページは、企業やお店が情報を載せる「広告の延長」として使われていました。しかし近年では、その役割が大きく変化しています。とくに行政との関わりや公的制度の申請時に、「ホームページの有無」が審査に影響する事例が増えているのです。
つまり、ホームページは今や「企業の信頼性を裏付ける存在証明」として不可欠になってきました。単に見栄えの良いデザインがあればいいというものではなく、その企業が社会ときちんとつながっているかを示す指標になっているのです。
「ホームページの有無」が問われるようになった現実
公的申請で「見せること」が求められる時代
2020年代に入り、企業活動の場面で「実態の可視化」が強く求められるようになりました。補助金申請や公的支援制度への応募においても、企業や個人事業主がどのような活動を行っているかを、客観的に確認できる情報源が必要とされています。この際、単なる自己申告や紙の申請書だけでは足りず、「自社で運営するホームページ」が重要な判断材料となることが増えています。
たとえば、国の補助金制度では「事業の内容が明確であるか」「社会にどう貢献しているか」といった要素が審査されることがあり、ホームページに掲載された事業紹介、過去の実績、取組内容などが有効な証拠として扱われます。フォームに「ホームページURLの記載欄」があるのはそのためです。
取引の入口としての「企業サイト」
公的機関に限らず、金融機関や取引先も、ホームページを企業評価の材料としています。銀行や信用金庫では、融資審査の初期段階でホームページをチェックするのが一般的になってきました。とくに新規取引の申し込みにおいては、紙の申請書や登記情報だけでなく、「ネット上でどのように情報発信しているか」「代表者の顔が見えるか」「事業が更新されているか」が判断基準になっています。
また、企業間の取引においても、受注者や協力企業を選定する際に、まずホームページがあるかどうかを確認するという行動が定着しつつあります。地域のビジネスマッチングイベント、各種事業者紹介サービス、行政主催の公開コンペなどでも、応募条件として「企業ホームページの開設」が明記されるケースが増えています。ホームページがないという理由だけで、そもそも選考に進めない――そんな事例も珍しくありません。
SNSやポータルサイトでは代用にならない理由
SNSでは「正確で整理された情報」が伝わらない
一部の事業者は、「うちはInstagramやX(旧Twitter)で発信しているから大丈夫」と考えるかもしれません。しかし、SNSは本来「タイムライン形式で流れていく即時性の高いツール」であり、企業の基礎情報や信用情報を安定的に届ける手段とは言い難いものです。
たとえば、会社概要・代表者名・設立年・所在地・沿革・事業内容・問い合わせ先といった情報を、SNSで一元的に表示するのは非常に難しいでしょう。プロフィール欄には文字数制限もあり、投稿は時間が経つとすぐに埋もれてしまいます。また、アカウントのなりすましや運営停止のリスクもあるため、審査機関や取引先にとっては、SNSだけでは事業実態を判断する根拠にならないのです。
さらに、SNSは匿名性が高いため、事業者の責任の所在が曖昧になりがちです。信頼性を判断するうえで、「誰が発信しているのか」がはっきりしない情報は、信頼構築には向いていません。
ポータルサイトは「補助的な情報」にとどまる
ポータルサイトに掲載された店舗情報や企業情報も、一見すると信頼できるように見えます。しかし実際には、これらのページの管理権限は運営企業にあり、情報の更新が事業者本人に完全に任されているわけではありません。情報が古かったり、営業を終了してもページが残っていたりするケースも少なくありません。
また、掲載情報には自由度がなく、企業としての理念や取り組み、沿革や代表者の顔が見えるような「独自性のある発信」が難しいというデメリットがあります。結果として、「掲載はされているが、責任の所在や発信の意図が見えない」状態になりがちです。
これに対して、自社で管理している独自ドメインのホームページは、掲載する情報の構成や文言に責任を持って運営でき、情報の正確性や更新頻度を自らコントロールできます。これは、社会的に「一次情報源」として扱われる根拠となり、信頼性の高い情報として評価されやすいのです。
たとえば、国のある公募制度では「企業の公式ウェブサイトを持っていること」が応募資格のひとつとして明記されており、ポータルサイトやSNSのURLを代用しても無効とされることがあります。このような例は今後さらに増えると見られ、企業の「情報インフラ」としてのホームページの必要性は高まり続けています。
「会社の格」を問われる時代へ
初めて取引を検討する際、相手企業のホームページが存在しているかどうかは、信頼性を測るひとつの判断材料になります。事業内容や実績、問い合わせ先が明記されているサイトがあれば、「しっかりとした事業者だ」という印象を与えます。
反対に、検索しても出てこない、あるいはホームページが存在しない場合、「本当にこの会社は存在しているのか?」「信用してよいのか?」という疑問を抱かせてしまいます。とくに法人格を持たずに活動している個人事業主や小規模事業者にとっては、「顔の見える発信媒体」としてホームページの整備が大きな信頼要素となるのです。
つまり、ホームページは単なる広報ツールではなく、「社会に対しての企業としての誠実さ」を示すものとして見られるようになっているのです。
補助金申請における評価要素としてのホームページ
たとえば「小規模事業者持続化補助金」の申請書では、販路開拓や情報発信の方法について記載する欄があります。ここで「自社ホームページを通じた情報発信」「お知らせの更新」などを具体的に記載することで、審査上の加点対象になる可能性があるのです。
さらに、「IT導入補助金」などでは、デジタルツールの導入効果を社会にどう伝えていくかも評価対象になります。こうした文脈において、自社ホームページでの取り組み紹介や成果発信は非常に重要です。採択後の事業報告書においても、成果をどう公表したか、発信媒体は何だったかを報告する必要があるため、「ホームページで成果を公開しています」という説明ができると説得力が高まります。
このように、補助金の申請から報告まで一貫して、ホームページが活用されることが求められる流れになっているのです。
「名刺代わり」から「社会的信頼の証」へ
昔は「とりあえず名刺にURLを載せるために作る」程度のホームページでも許されました。しかし、現代ではホームページがなければ、そもそも商談の入口に立てない、信頼されない、という時代になりつつあります。
多くの人が企業をネットで調べるようになった今、「会社名で検索しても出てこない」「情報が古い」「更新されていない」という状況では、ネガティブな印象を与えかねません。
また、ホームページを自社で管理・更新できていることは、情報発信能力や体制の整備状況を判断するうえでもプラスに働きます。行政側も、「きちんと情報公開できる事業者かどうか」を重視するようになってきており、その意味でもホームページの存在は重要な役割を担っているのです。
今後ますます強まる「見える化」の圧力
電子申請やペーパーレスが推進されるなか、企業の実態や信頼性を「見える形」で示すことが求められるようになっています。これは単に法律の問題ではなく、「選ばれる企業」「支援される企業」になるための条件ともいえるでしょう。
たとえば、ホームページにプライバシーポリシーや特定商取引法の表記があると、法令を遵守している姿勢が伝わります。代表者の挨拶や企業理念が掲載されていれば、事業への思いが見えることで共感を得られやすくなります。SDGsや地域活動への取り組みを紹介していれば、社会貢献の姿勢も明確になります。導入事例やお客様の声があれば、実績の裏付けとなり、初見の相手にも安心感を与えることができます。
これらはすべて、SNSや無料ブログではなかなか伝えきれない要素です。情報の正確性、更新の継続性、そして構造化された掲載――これらすべてを実現するには、やはり公式なホームページが欠かせないのです。
結論:ホームページは「社会と接続する基盤」
ホームページがなければ、情報が不完全に見られるだけでなく、信用や機会までも失ってしまうリスクがある――これが現代における現実です。とくに、公的支援制度や行政との関係構築を視野に入れている事業者にとっては、「ホームページの有無」が致命的な差を生みかねません。
ホームページは今や、事業者が社会と接点を持つための「窓口」であり、「信頼の証明書」でもあります。「まだ持っていない」「放置してしまっている」という場合には、今すぐにでもその存在意義を見直し、整備・活用を始めるべきタイミングに来ているといえるでしょう。
このコラムを書いた人

さぽたん
ホームページに関するお困りごと、
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください!