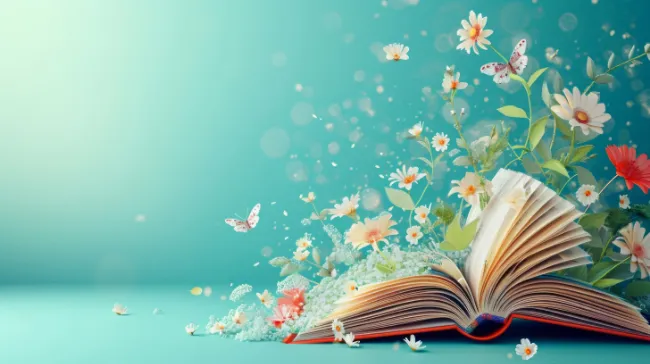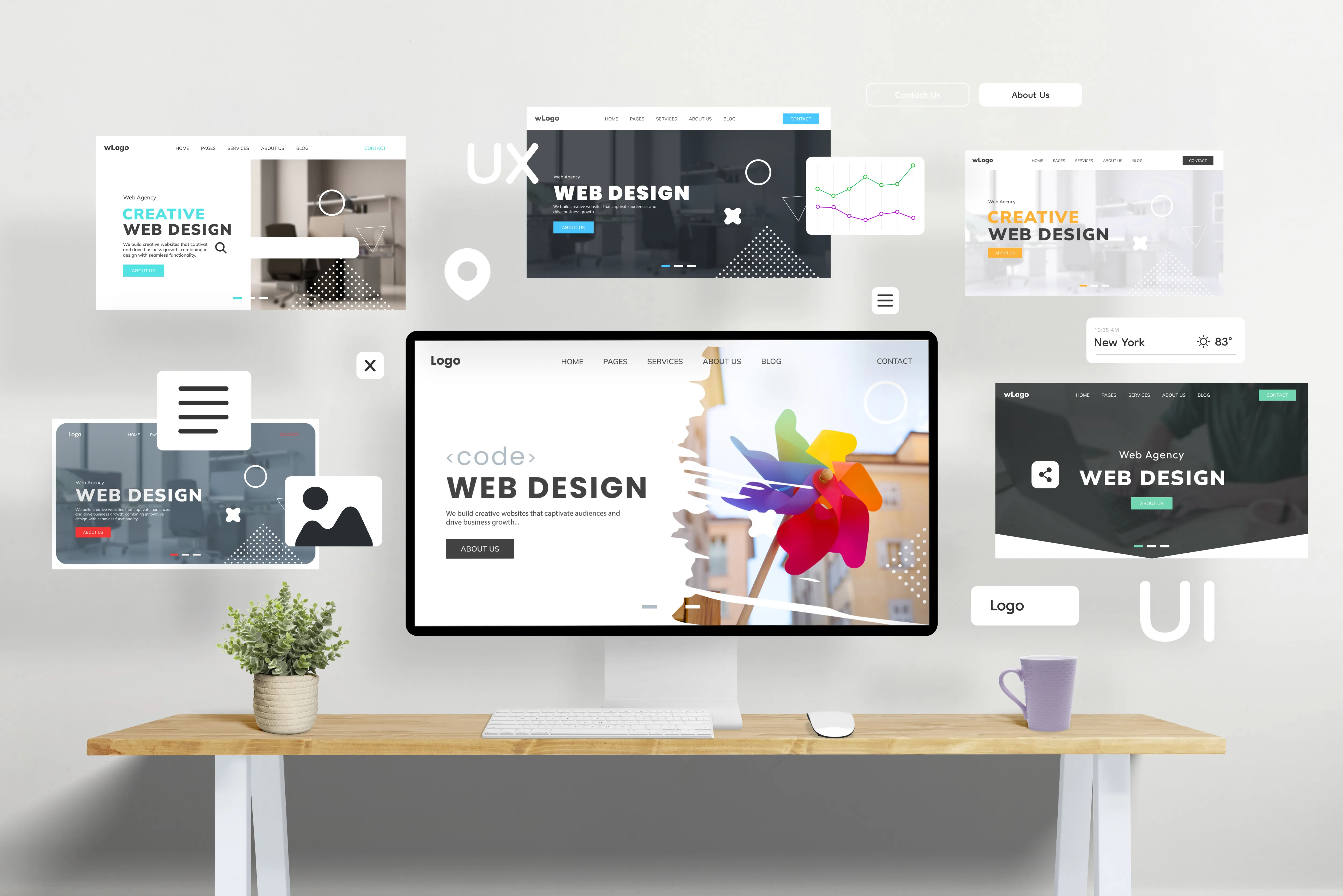スタートしたばかりの企業がホームページに載せるべきこと
目次
はじめに
企業がスタートしたばかりの段階では、まだ実績や知名度が十分に整っていないため、外部からの信頼をどう獲得していくかが大きな課題になります。そんな中で、ホームページは「存在を証明する名刺」としての役割を果たすと同時に、「信頼を生む営業マン」のような存在にもなります。しかし、何を載せればよいのかわからないという方も少なくありません。
このコラムでは、創業初期の企業がホームページに載せるべき情報を、具体的にそして信頼性を高める観点から丁寧に解説していきます。
ホームページは「信用の土台」となる
まず前提として、創業間もない企業にとって、ホームページは単なるデザインの綺麗な宣伝ツールではありません。お客様や取引先が、企業の実在性や信頼性を確認する第一の手段になります。名刺交換の後に検索され、電話営業後に企業名を入力され、あるいはSNSで偶然見かけて興味を持たれた時、その確認先として必ずと言っていいほどアクセスされるのがホームページです。
そのため、「どのような理念で」「誰に向けて」「どのような価値を提供しているのか」をしっかりと伝えることが最も重要です。情報量が少ないスタートアップだからこそ、曖昧な表現を避け、誠実で具体的な説明を心がける必要があります。
会社概要で「実在する企業」であることを示す
創業初期に必ず整えておきたいのが「会社概要」です。これは法人でも個人事業でも必要です。企業としての基本的な情報を明記することで、訪問者に安心感を与えることができます。具体的には、企業名と代表者名はもちろん、所在地や電話番号、メールアドレスなどの連絡先もはっきりと表示すべきです。
また、設立年月日や資本金、事業内容なども記載すると、企業の実体がより明確になります。事業内容については一言で済ませるのではなく、「どんな領域で、どんな形で社会に関わっているか」が伝わるように丁寧に書きましょう。信頼は「情報の透明性」から始まるということを、会社概要ページでは常に意識するべきです。
代表挨拶や創業ストーリーで「想い」を伝える
まだ知名度がない企業だからこそ、「誰がこの会社を動かしているのか」が非常に重要になります。その意味で、代表者のメッセージや創業ストーリーは、ホームページにおける核のひとつです。
たとえば、「なぜこのビジネスを始めたのか」「どのような課題意識を持って起業したのか」「これからどんな会社を目指しているのか」といった想いを、代表者自身の言葉で記述することで、訪問者との距離感を縮めることができます。こうした人間味あふれる情報は、無機質な会社紹介とは違い、共感や応援を生みやすく、創業初期における貴重な武器になります。
サービス・商品紹介では「誰のための何か」を明確に
ホームページを訪れた人が最も知りたいのは、「この会社は自分にどんな価値を提供してくれるのか」という点です。たとえ創業間もないとしても、自社のサービスや商品の特徴、対象とする顧客層、導入の流れ、価格帯などをできるだけ具体的に説明する必要があります。
たとえば、商品やサービスの名称をしっかり明示したうえで、その内容がどんな特徴を持っているのか、どのような点で他社と差別化できているのかを紹介すると、読み手は自分に合っているかどうかを判断しやすくなります。また、「このサービスはこんな悩みを持った人に向けて作られています」といった記述も、ターゲットを明確にする手助けになります。
価格については、明記することで「問い合わせ前の心理的ハードル」を下げる効果があります。定価を記載できない場合でも、参考価格や料金の目安を掲載すると、信頼性の向上につながります。
実績がなくても「できること」「得意なこと」を伝える
創業して間もない企業の多くは、まだ顧客の声や導入事例などの“証拠”を持っていない場合があります。しかし、だからといって何も載せられないというわけではありません。
たとえば、創業前に取り組んでいた関連分野での活動や、これまでに個人で手がけた案件の経験がある場合は、それを補足情報として掲載することで信頼性を補うことができます。今後取り組んでいきたい分野や、開発中のサービスがあれば、それを正直に紹介することもひとつの方法です。さらに、試作品やプロトタイプ、ポートフォリオなどがあれば、写真付きで紹介することで、自社の技術力や品質へのこだわりを伝えることができます。
スタート段階で大切なのは、「まだ経験が浅いから何も書かない」のではなく、「現時点でできることを誠実に伝える」という姿勢です。
よくある質問で「問い合わせ前の不安」を和らげる
見込み顧客の中には、問い合わせをする前に「こんなこと聞いても大丈夫だろうか」と不安を感じる人が少なくありません。そこで役立つのが「よくある質問(FAQ)」ページです。
たとえば、「このサービスを利用するには何を準備すればよいか」「納品までにどのくらいかかるのか」「小規模な依頼でも受けてもらえるのか」「オンラインでの相談に対応しているか」など、初めての顧客が気にしそうな質問に対して、事前に丁寧に答えておくことで、問い合わせのハードルを下げることができます。
FAQは、直接的な営業トークとは違い、顧客の疑問や不安に寄り添った情報提供の場であり、自然な信頼構築につながる仕掛けでもあるのです。
問い合わせフォームは「シンプルさ」が決め手
ホームページのゴール地点ともいえるのが「お問い合わせフォーム」です。どれだけ興味を持ってもらえても、フォームが複雑で入力が面倒だったり、スマホで表示が崩れていたりすると、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。
理想的なフォームは、氏名、連絡先、相談内容の3項目程度で構成されており、必要最低限の入力だけで送信できるようになっているものです。さらに、自動返信で「お問い合わせを受け付けました」といった確認メールが届くようになっていれば、安心感も生まれます。
また、個人情報の取り扱いに関して不安を抱かれないよう、「プライバシーポリシー」へのリンクをフォーム近くに設置しておくのも忘れてはいけません。
SNSやブログとの連携で「会社の動き」を見せる
創業初期は、ホームページ上の情報がどうしても静的になりがちです。そこで、SNSやブログを活用することで、会社が日々どのように動いているのかを発信していくことが重要になります。
たとえば、新サービスの準備風景や、初めての受注を報告した内容、スタッフの紹介や日々の気づきなどを定期的に更新することで、企業の活動が見える化され、訪問者に「この会社は動いている」という印象を与えることができます。
こうした更新情報は、単に情報を伝えるだけでなく、企業の温度感や価値観を伝える役割も果たします。とくに創業者の人柄が伝わるような内容は、信頼関係の構築に大きく貢献します。
法的表記を忘れずに整備する
ホームページには、法的な義務として掲載しなければならない情報もあります。たとえば、個人情報の取り扱いに関する「プライバシーポリシー」や、物販や請負業務などを行う場合に必要となる「特定商取引法に基づく表記」などです。
プライバシーポリシーでは、問い合わせフォームを通じて取得した個人情報をどのように管理し、どのような目的で使用するかを明記します。また、特定商取引法の表記では、販売事業者名、所在地、連絡先、返品・交換の対応方針などを掲載する必要があります。
こうした情報を適切に整備することは、信頼を得るための最低限のマナーであると同時に、トラブルを未然に防ぐ法的リスク管理でもあるのです。
まとめ:少ない情報だからこそ、「誠実さ」と「明確さ」を
創業間もない段階では、どうしても情報量が限られます。しかし、その状況に甘んじるのではなく、限られた情報の中でいかに誠実に、そして明確に伝えるかが信頼の分かれ道になります。
「実績がないからこそ、想いを語る」「まだ商品が整っていないからこそ、準備状況を開示する」――その姿勢に共感し、最初の顧客やパートナーが現れるのです。
ホームページは、会社の姿勢や価値観を映し出す鏡です。スタートの段階からしっかりと設計されたホームページは、これからの成長に欠かせない資産になります。信頼される第一歩として、今ある情報で最大限の表現を心がけていきましょう。
このコラムを書いた人

さぽたん
ホームページに関するお困りごと、
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください!