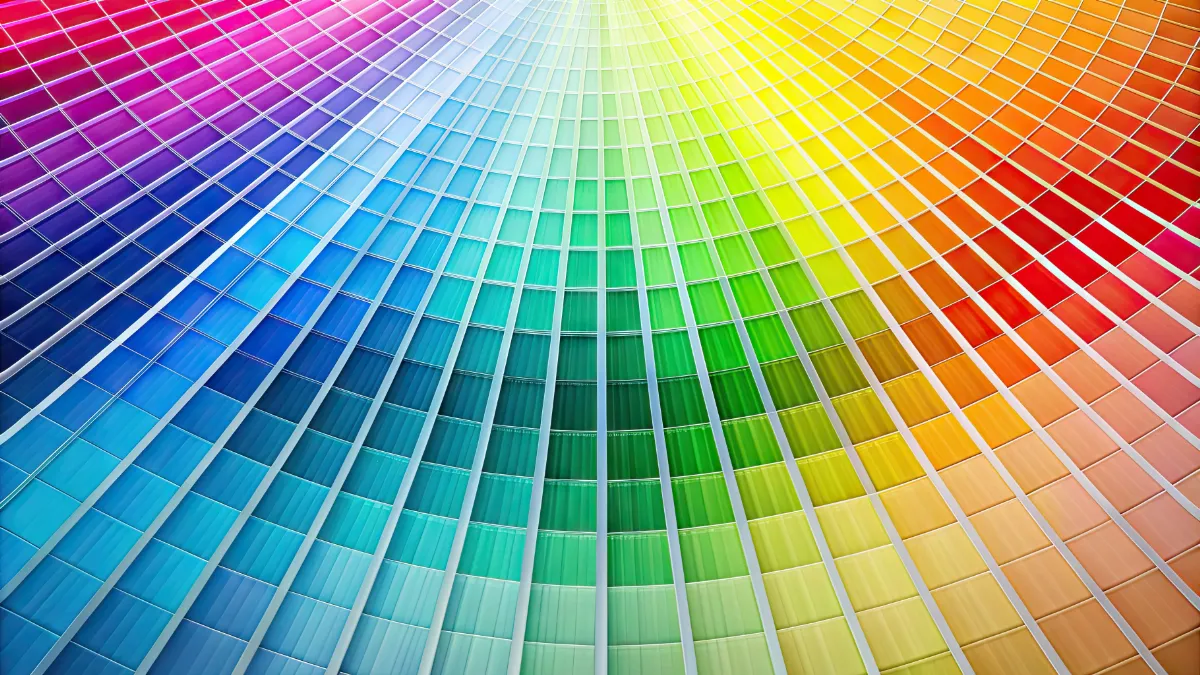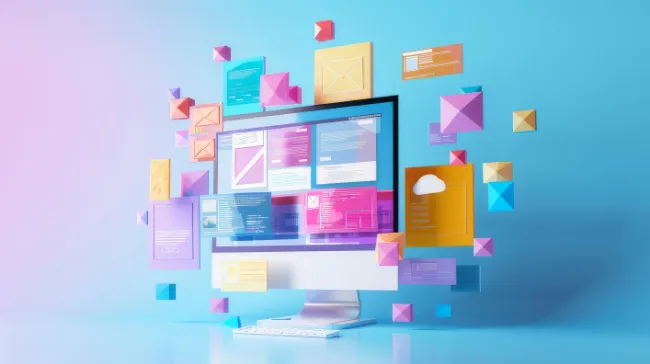TOPページのスライドショー、どのくらい見てもらえるものなのか?
目次
はじめに:スライドショーは本当に効果的か
ホームページ制作では、TOPページにスライドショー(カルーセル)を設置するケースが多く見られます。複数のキャンペーンやサービスを同時に紹介できるため、企業側にとっては「見せたい情報をまとめて表示できる便利な機能」として重宝されます。しかし、実際にユーザーはどのくらいスライドを見ているのでしょうか。データやユーザー行動の研究を踏まえながら、スライドショーの現実的な効果を検証し、導入する際の注意点を掘り下げていきます。
スライドショーの閲覧実態:1枚目がほぼ全て
スライドショーの実際の閲覧状況を把握するには、ユーザーの視線の動きやクリックデータといった具体的な解析結果を見るのが有効です。UXの分野で知られるNielsen Norman Group(NNG)の調査によれば、カルーセルの1枚目は非常によくクリックされる一方、2枚目以降になるとクリック率は急激に低下します。ある大手ECサイトの実験では、1枚目が全クリックの約90%、2枚目が約7%、3枚目以降は合わせても3%未満という結果が出ています。
この現象は、ユーザーの「注意資源の有限性」によって説明できます。人は新しいページにアクセスすると、まずファーストビューで自分が求める情報があるかどうかを判断します。この判断はほんの2〜3秒で行われるため、スライドショーが自動で切り替わるタイミングまで待たずにスクロールを開始してしまうのです。特にスマートフォンでは画面が小さく、1枚目を見ただけで下へスクロールする傾向がより強く見られます。
また、視線計測(アイトラッキング)の研究では、ユーザーの視線はページ上部から左上→中央→右上と移動し、次に下方向へ流れていくパターンが多いことが確認されています。スライドショーのナビゲーションボタンやページ番号は端に配置されることが多く、そもそも視線が届かないまま通り過ぎるケースも少なくありません。結果として、1枚目以降のスライドは存在していても「見られないコンテンツ」になりやすいのです。
ファーストビューと滞在時間の関係
ユーザーの滞在時間は、スライドショーの閲覧率に大きな影響を及ぼします。多くの解析データでは、TOPページの平均滞在時間は30秒から1分程度にとどまるとされます。しかも、この時間はページ全体に対するものであり、スライドショーだけに割かれる時間はそのごく一部です。
仮にスライドが5秒ごとに切り替わる設定だったとして、1枚目が表示されるのに5秒、2枚目が表示されるまでさらに5秒かかるとすると、2枚目がユーザーの視界に現れるのはページ到達から10秒後です。平均的なユーザーはすでにその時点でスクロールを終え、別の情報に目を向けている可能性が高いため、2枚目以降のスライドが実際に読まれる確率はどんどん下がっていきます。
このことは、特にキャンペーンや重要なお知らせをスライドショーの2枚目や3枚目に配置している場合に大きなリスクとなります。「告知したはずなのに、問い合わせが少ない」「イベント情報がユーザーに届いていない」という結果を招きかねません。
自動再生と手動操作の違い
スライドショーには自動再生と手動操作の2つの形態がありますが、ユーザーが自発的にスライドを送る頻度は非常に低いのが現実です。ある解析事例では、カルーセルの矢印ボタンやドットナビゲーションをタップしたユーザーは全体の1〜2%にとどまりました。
これは特にスマートフォン環境では顕著です。スマホの画面ではナビゲーションボタンが小さく、指でタップしづらい位置にあることも多いため、ユーザーは気づかないか、気づいても操作しない傾向があります。結果として、サイト管理者が意図した「順番に見てもらう体験」はほとんど実現していないことになります。
さらに、ユーザーがスライドを手動で送る場合でも、2枚目までが限界というケースが多く、3枚目以降まで進む人はごく一部です。つまり、5枚も6枚もスライドを用意しても、その大半はほぼ見られずに終わる可能性が高いということです。
スライドショーが抱えるデメリット
スライドショーには、見栄えや情報集約というメリットがありますが、それ以上に考慮すべきデメリットが存在します。まず、複数の大きな画像を読み込むため、ページの表示速度が遅くなる可能性があります。Googleが発表したデータによれば、読み込みが1秒遅くなるごとにコンバージョン率が7%ずつ低下するとも言われており、表示速度の遅さは直接的な機会損失につながります。
次に、SEOへの影響です。スライドショーのテキストが画像として埋め込まれていると、検索エンジンがその内容を認識できず、検索順位に貢献しない場合があります。特に地域名やサービス名などの重要なキーワードが画像にしか含まれていない場合、SEO上の大きな損失になりかねません。
さらに、情報の優先順位が曖昧になる点も問題です。社内調整の結果として複数の部署やサービスを公平に扱うためにスライドを増やした結果、ユーザーから見れば「どれが重要なのかわからない」「情報が多すぎて混乱する」という印象を与えてしまうことがあります。
効果を高めるための工夫
それでもスライドショーを活用する場合は、いくつかの工夫が有効です。もっとも重要なのは、1枚目に最も優先度の高い情報を配置することです。キャンペーン、主要サービス、新製品など企業として一番訴求したい内容を1枚目に集約し、確実にユーザーに届けます。
切り替え速度は3〜5秒程度が適切とされます。早すぎると読み終わる前に次のスライドへ進んでしまい、遅すぎるとユーザーが待てずに離脱してしまいます。さらに、各スライド全体をクリック可能なリンクに設定することで、ユーザーが迷わずアクションできるようにするのも効果的です。
また、画像サイズの最適化やLazy Loadによる遅延読み込みを導入し、ページ表示速度を犠牲にしない工夫も欠かせません。スマホでの表示を前提に、ナビゲーションボタンのサイズや位置も調整することで、操作性を高めることができます。
代替案:静止ビジュアル+明確な導線
最近では、スライドショーではなく、1枚の強いメインビジュアルと複数のリンクボタンやカード型コンテンツを組み合わせるデザインが好まれています。この方法なら、ユーザーは自分の興味関心に応じてクリックでき、待たされるストレスがありません。
特にスマホユーザーは、縦スクロールに慣れているため、複数の情報を縦に並べたほうが視認性が高く、結果的に情報到達率も向上します。スライドショーが「受け身で見せる」設計なのに対し、静止ビジュアルとリンク導線は「ユーザーに選ばせる」設計であり、能動的な行動を引き出しやすいという利点があります。
データに基づいた判断のすすめ
スライドショーを残すべきか、それとも静止ビジュアルに切り替えるべきか迷う場合は、感覚ではなくデータで判断することが大切です。A/Bテストを実施して、スライドあり・なしのクリック率、滞在時間、CVR(コンバージョン率)を比較すれば、どのデザインが実際に成果を出しているか明確になります。
例えば、スライドショーを削除して静止ビジュアルに置き換えた結果、問い合わせ数が20%増加した、ページ滞在時間が伸びたといった事例も存在します。Google Analyticsやヒートマップツールを活用すれば、ユーザーがどこをクリックしているか、どこで離脱しているかが把握できるため、改善の裏付けとして非常に有効です。
まとめ:1枚目勝負で設計する
結論として、TOPページのスライドショーは2枚目以降の閲覧率が低く、1枚目が勝負どころと言えます。多くのユーザーはページ到達後すぐにスクロールや離脱を行うため、見せたい情報は最初の1枚に凝縮することが重要です。複数の情報を詰め込みたい場合は、下部にわかりやすい導線を設けるなど、ユーザーが能動的に選べるデザインを心がけましょう。スライドショーは便利なツールですが、過信せず、実際のユーザー行動に基づいて設計することが、成果の出るホームページ制作には欠かせません。
このコラムを書いた人

さぽたん
ホームページに関するお困りごと、
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください!