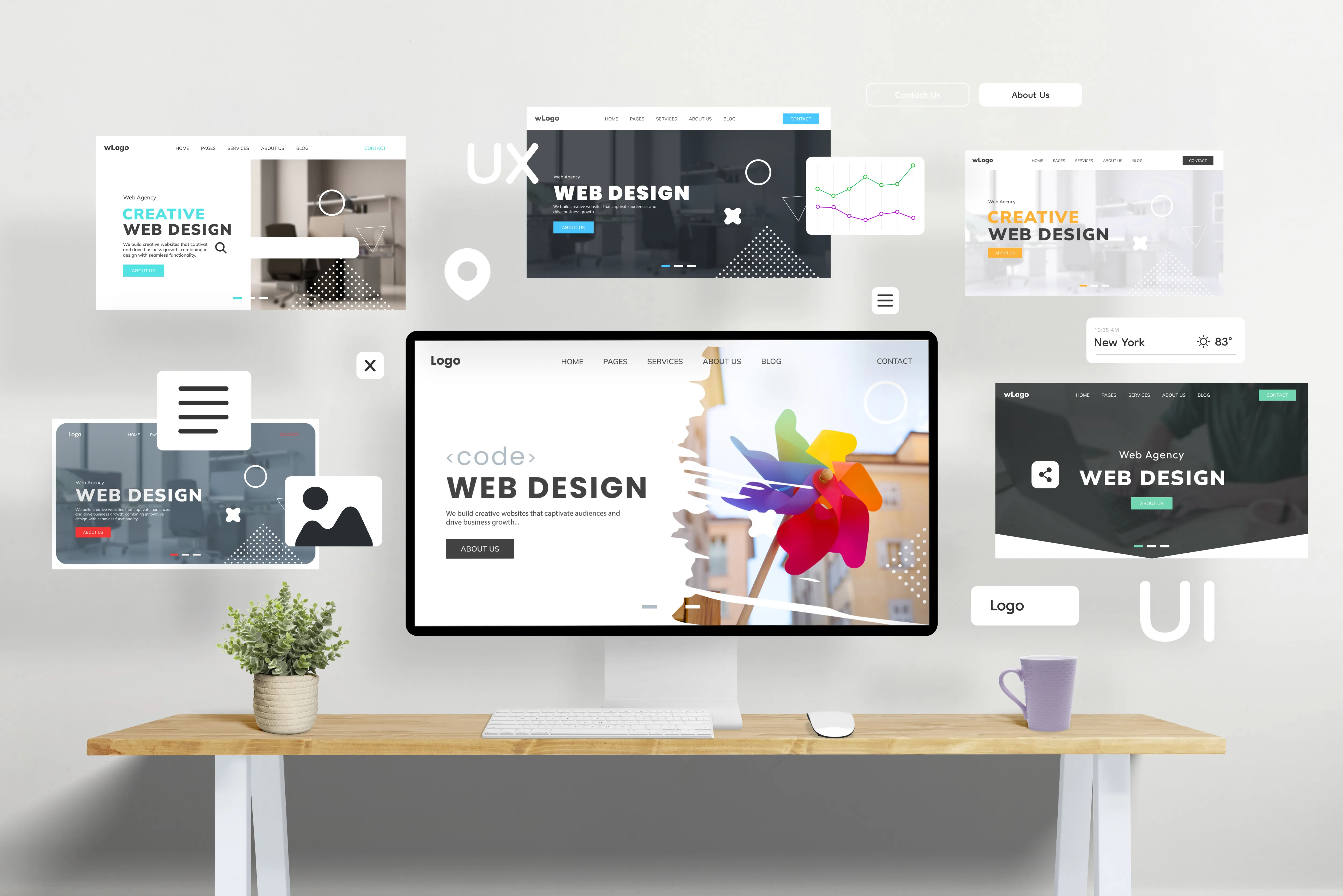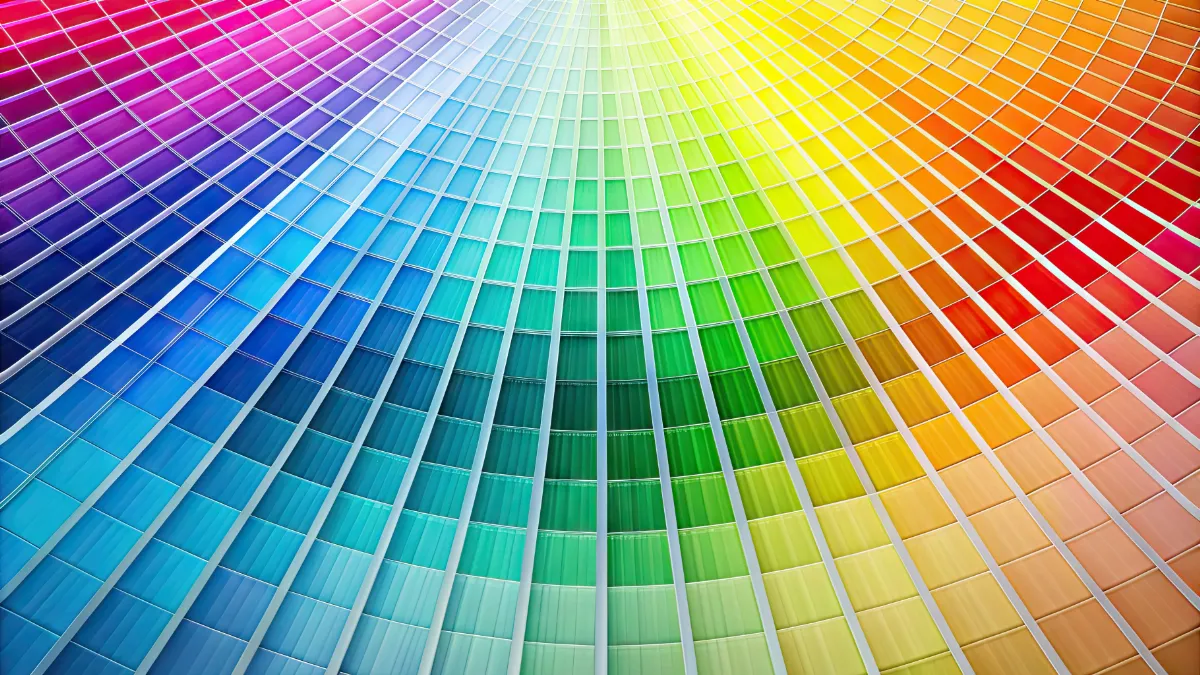ホームページ制作でありがちな「やりすぎデザイン」の落とし穴
目次
「やりすぎデザイン」の落とし穴とは
ホームページを制作する際、多くの人がまず意識するのが「デザイン性」です。目を引くデザイン、美しいビジュアル、動きのある演出は、ユーザーの第一印象を決定づけるため、力を入れたくなる気持ちは非常によくわかります。しかし、デザインにこだわるあまり、情報の伝達性やユーザーの使いやすさを損なってしまうケースも少なくありません。いわゆる「やりすぎデザイン」の落とし穴です。
これは、見た目が派手であったり、技術的に凝っていたりする一方で、訪問者が必要な情報にたどり着けなかったり、ページ表示が遅くなったりするなど、実用性の面で多くの弊害を生みます。今回は、ホームページ制作における「やりすぎデザイン」とは何か、その具体的な問題点、そして防ぐための考え方について、実例を交えて詳しく解説していきます。
デザインにこだわりすぎて失う「使いやすさ」
一見魅力的に見えるデザインでも、実際にサイトを使う人にとっては不親切であることが少なくありません。例えば、背景と文字の色のコントラストが弱く、文章が読みづらいサイトでは、たとえどれだけ洗練されたデザインであっても情報が届かなくなってしまいます。また、フォントサイズが小さすぎたり、装飾文字が多すぎたりすると、読み進めるだけでも疲れてしまい、途中で離脱される原因となります。
さらに、近年増えているのが、アニメーションやエフェクトを多用した演出です。スクロールに応じて画像や文字がふわっと現れたり、ページ全体が左右にスライドしたりするような仕掛けは、一度は「おしゃれ」と感じられるかもしれません。しかし、こうした演出が多すぎると、操作にストレスを感じたり、動きに目が追いつかず酔ってしまう人も出てきます。特にスマートフォンなど小さな画面で見る場合、操作性はさらに悪化します。
本来の目的が見えなくなる危険性
ホームページにはそれぞれ明確な目的があります。会社であれば「企業の信頼感を伝える」、店舗であれば「来店や予約の促進」、サービス業であれば「問い合わせや申込の獲得」などが主な目的でしょう。しかし、過剰なデザインによって、その目的がぼやけてしまうことがあります。
たとえば、訪問者がページを開いたとき、どこから情報を得ればいいのか、どこをクリックすれば目的のページにたどり着けるのかがわからないような構造になっていると、ユーザーは迷い、すぐに離れてしまいます。特に「お問い合わせ」や「購入」の導線が見つけづらいケースは致命的です。目立たせるべきボタンやリンクが背景と同化していたり、デザインを優先するあまりに独特なアイコンやメニューになっていたりすると、ユーザーの行動を妨げる結果となります。
また、装飾的な画像や動画が多すぎることで、肝心のメッセージが伝わらない場合もあります。画像が多くて印象的なページだとしても、文字情報がほとんどなく、検索エンジンに正しく読み取られない構造になっていると、SEO的にも不利になります。
SEOやアクセシビリティへの悪影響も
過剰なビジュアルは、検索エンジンや閲覧環境によっては逆効果になります。画像に文字を埋め込んでしまうと、その内容はGoogleのクローラーに認識されません。また、JavaScriptで表示される動的なコンテンツも、環境によっては表示されなかったり、SEO評価に反映されなかったりすることがあります。
さらに、ページの読み込みが遅くなるという問題も無視できません。重たい画像や動画、複雑なスクリプトは、表示速度に直接影響します。Googleがページ表示速度をランキング要因のひとつとしていることはよく知られていますが、訪問者にとっても表示の遅いページはストレスになります。3秒以上かかると約半数が離脱するというデータもあり、見た目にこだわった結果、閲覧すらされないページになってしまっては元も子もありません。
また、視覚的な要素に頼りすぎたデザインは、アクセシビリティの観点からも問題があります。色覚異常のある方にとって見えにくい配色になっていたり、音声読み上げソフトに対応していない設計になっていたりすると、一部のユーザーを排除するサイトになってしまいます。現代のウェブサイトは、年齢・性別・障害の有無を問わず、誰にでも開かれた構造であることが求められています。
運用や更新が難しくなるという現実
デザインに凝りすぎると、公開後の運用や更新が非常に大変になります。たとえば、複雑なレイアウトや特殊な演出が含まれている場合、ページの一部を変更するだけでも、制作者やエンジニアに依頼しなければならないことが増えます。CMSを導入しているにもかかわらず、管理画面から簡単に編集できない構成になってしまっているケースもよく見られます。
また、トレンドを反映したデザインは一見華やかですが、数年後には「古臭い」と感じられてしまう可能性があります。たとえば、フラットデザイン、マテリアルデザイン、グラスモーフィズムなど、近年も次々と流行が変化していますが、それに追従するためには頻繁なリニューアルが必要になり、コストや手間がかかります。
流行より「目的達成」に重きを置く発想へ
本当に成果を出すホームページに必要なのは、「おしゃれさ」よりも「目的達成のしやすさ」です。もちろん、最低限のビジュアルの整備は必要ですが、それはあくまで「伝えるための手段」に過ぎません。訪問者が何を求めていて、どうすればその目的にスムーズに到達できるかを常に考えるべきです。
例えば、商品を販売したいページであれば、購入ボタンを目立たせるために、装飾よりも色や配置の工夫を優先するべきです。会社紹介ページであれば、代表者の顔や社屋の写真、理念など、信頼につながる情報をストレートに伝えることが重要です。サービス案内であれば、料金や所要時間、対応エリアなどの「決め手」となる情報をわかりやすく提示すべきです。
デザインの力を最大限に活かすには、「視覚的な装飾」ではなく「機能的なデザイン」という視点を持つ必要があります。つまり、ユーザーが迷わず行動できるように導くレイアウト、視線を自然に誘導する情報設計、そしてデバイスに応じた表示最適化こそが、成果に直結するデザインなのです。
本当に成果が出るホームページとは
最終的に、成果を出すホームページは、見た目よりも“中身”と“使いやすさ”に重きが置かれています。見た目にインパクトがあっても、問い合わせにつながらないサイトでは意味がありません。反対に、シンプルなデザインでも、情報が的確に伝わり、問い合わせや購入につながるのであれば、それが「正解」と言えるでしょう。
見せかけの派手さではなく、「ユーザーにとって快適であること」「目的に対して最短で行動できること」「誰にとっても使いやすい構造であること」。この3つが揃ってこそ、真に効果的なホームページだといえます。
まとめ:引き算の美学で成果を引き出す
ホームページ制作では、「もっと見せたい」「もっと目立たせたい」といった足し算の発想に陥りがちです。しかし、成果を求めるのであれば、むしろ「何を削るか」「何を簡略化するか」といった引き算の視点が重要です。余計なものをそぎ落とし、本当に伝えたいことだけを、使いやすい形で提示することが、信頼や行動を引き出す鍵になります。
やりすぎたデザインは、短期的にはインパクトを残すかもしれませんが、長期的な信頼や成果を得るうえではむしろ障害になり得ます。必要なのは「ちょうどいいデザイン」であり、それは見た目と機能のバランスが取れた、ユーザー中心の設計です。
この視点を持つことができれば、デザインに悩むことがあっても、「本当に必要な表現」を取捨選択できるようになるはずです。そして、それこそがビジネスを支えるホームページ制作において、最も大切な判断基準となるでしょう。
このコラムを書いた人

さぽたん
ホームページに関するお困りごと、
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください!