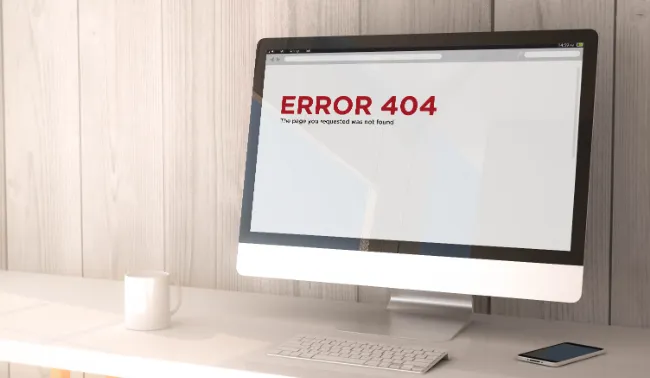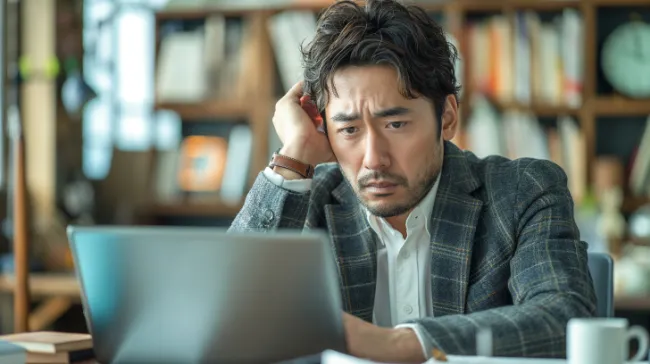
Googleに嫌われるページの特徴
目次
はじめに
「せっかくホームページを作ったのに、なかなか検索で上がらない」「昔は上位にいたのに、最近順位が落ちている」。
そう感じたことがある方は多いのではないでしょうか。検索順位を決めるのはGoogleのアルゴリズムですが、その根本にある考え方は一貫しています。Googleは「ユーザーにとって価値ある情報を届けるページ」を上位に表示し、反対に「信頼を損なうページ」を下位へ押し下げます。
では、Googleが「嫌うページ」とは、どんな特徴を持っているのでしょうか。
コンテンツの質が低いページ
Googleが最も重視しているのは「コンテンツの品質」です。単に文字数が多いとか、キーワードがたくさん入っているといった表面的な要素ではなく、「読者にとって本当に役立つ情報か」が問われます。
たとえば、他サイトの内容をコピーした記事や、AI生成文をそのまま貼り付けただけのような文章は評価されません。Googleは独自性と専門性を重視しており、E-E-A-T(Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthiness)という評価軸を基準に、ページの信頼性を判断しています。
「体験に基づいた具体的な説明」や「一次情報の提供」がないページは、内容がどれだけ長くても検索結果では不利になります。つまり、“書き手の実体”が見えるかどうかがポイントなのです。
キーワードを詰め込みすぎている
かつては「SEO=キーワードの多用」と考えられていました。しかし現在では、キーワードの乱用は逆効果です。Googleは「不自然な繰り返し」や「検索エンジンを意識しすぎた文体」を見抜く能力を持っています。
たとえば、
「埼玉 ホームページ制作 おすすめ 埼玉 ホームページ制作 安い」
といった文章は、人が読んでも違和感を覚えます。こうした“キーワードの詰め込み”は、ユーザー体験を損なうため、スパム行為としてマイナス評価を受けることがあります。
自然な文脈の中でキーワードを散りばめ、読者がスムーズに理解できる文章を意識することが、今のSEOでは求められています。
見る人のことを考えていない設計
Googleはページ内容だけでなく、「使いやすさ」も評価の対象としています。表示速度が遅い、スマートフォンで文字が読みにくい、リンクが押しづらい——そういった要素があると、Googleは「ユーザーに優しくないページ」と判断します。
特にモバイルファーストインデックス(MFI)が導入されて以降、スマートフォンでの閲覧体験は評価に直結します。デザインや構成が古く、スマホ対応が不十分なサイトは、検索順位が落ちやすい傾向があります。
また、ポップアップや広告が過剰に表示されるページも注意が必要です。ユーザーが求める情報にたどり着く前に広告で遮られてしまうと、直帰率が上がり、Googleは「価値の低いページ」と判断します。
更新されていない古い情報のページ
「情報の鮮度」もGoogleが重視するポイントです。
たとえば、2018年のデータをそのまま掲載していたり、すでに存在しない店舗情報を放置していたりすると、ユーザーに誤解を与えるだけでなく、Googleの信頼も失います。
検索エンジンは「定期的に更新されている=管理が行き届いたサイト」と判断します。逆に、何年も更新されていないページは、「放置されている」「内容が古い」とみなされ、順位が下がることがあります。
特に、業界動向が早い分野や価格変動が激しい業種では、情報の更新頻度がSEOに直結します。ブログやお知らせページで最新情報を発信することは、検索順位を維持するためにも有効です。
他サイトへのリンクが不自然・信用できない
リンクの貼り方も、Googleがページの信頼性を判断する材料になります。たとえば、関連性のない外部サイトへ大量にリンクしている場合や、アフィリエイト目的の不自然なリンクが多い場合は、検索エンジンから「スパム的」と見なされる可能性があります。
また、nofollowタグを付けるべき広告リンクにそれが設定されていないと、「ランキング操作」とみなされることもあります。
一方で、信頼できる公的機関や専門メディアへのリンクは、コンテンツの裏付けとして評価される傾向にあります。リンクは“数”ではなく“質”が問われる時代です。
コピーコンテンツや重複ページが多い
同じ内容のページを複数公開していると、Googleはどれを評価すべきか判断できず、結果的に全ページの評価が下がります。特にWordPressなどのCMSでは、タグページやカテゴリーページが自動生成されるため、知らないうちに「重複コンテンツ」が発生しているケースがあります。canonicalタグを正しく設定し、オリジナルのページを明示することが重要です。
また、他サイトの文章を引用する場合も、引用タグを使い、自分の言葉で補足説明を加えることが求められます。単なるコピーや転用では、Googleから「独自性がない」と判断されてしまうのです。
ガイドラインに反するSEO施策
リンクの売買や自作自演の被リンク、隠しテキストなど、いわゆるブラックハットSEOと呼ばれる手法は、Googleのポリシーで明確に禁止されています。
短期的に順位を上げることはできても、発見された時点でペナルティを受け、インデックスから削除されることもあります。Googleは年々、こうした不正を見抜く精度を高めています。AIによる文体検出、被リンクの自然度分析などが進化しており、“ごまかし”は通用しなくなりました。
検索順位を上げたいなら、遠回りでも「正しい方法」で信頼を積み重ねることが最も効果的です。
ユーザーの滞在時間が短く、離脱率が高い
Googleは直接的に「滞在時間」や「離脱率」を公開してはいませんが、ユーザー行動の分析は評価指標の一部とされています。検索結果からページを開いてすぐに戻る(いわゆる“ポゴスティッキング”)行動が多いページは、満足度が低いと判断されやすいのです。
内容が薄い、構成が分かりづらい、画像ばかりで文字情報がない、といった要因が離脱を招きます。読者がページを最後まで読めるように、見出し構成を工夫したり、冒頭で内容を明示したりすることが、間接的にSEOを改善します。つまり、「人が読みたくなるページ」は「Googleにも好かれるページ」なのです。
セキュリティが不十分なページ
現在、GoogleはHTTPS化されていないサイトに「保護されていません」という警告を表示します。SSL対応(URLがhttpsで始まること)は、検索順位の評価基準にも組み込まれています。
セキュリティが不十分なページは、ユーザーだけでなくGoogleにとってもリスク要因とみなされます。フォーム送信時の暗号化が行われていなかったり、マルウェアが含まれていたりすると、インデックス対象から除外される可能性もあります。
特に企業サイトやECサイトでは、SSL証明書の更新期限にも注意が必要です。セキュリティ対策はもはや“オプション”ではなく、Googleが定める最低限の信頼条件になっています。
構造が整理されていない・内部リンクが乱雑
Googleはクローラーによってページを巡回し、内容を理解します。その際に、内部リンクの構造が複雑だったり、ナビゲーションが不明確だったりすると、サイト全体の評価が下がります。
特に、「トップページから重要ページにたどり着けない」「URL構造がバラバラ」「パンくずリストがない」といった状態は、検索エンジンにとって理解しにくいサイトになります。また、titleタグやmeta descriptionの重複も、クローラーの混乱を招く要因です。
サイト構造を整理し、論理的にページがつながっていることが、SEOの基本です。これは人間の読みやすさにも直結します。
広告や自動再生が多くストレスを与える
Googleは「ユーザーにストレスを与えるページ」を好みません。
突然動画が再生されたり、ポップアップ広告が何度も出てきたりするサイトは、ユーザー体験を損なう典型です。Googleの「ページエクスペリエンスアップデート」でも、インタースティシャル(全画面広告)や音声の自動再生は明確にマイナス評価とされています。
広告の掲載は収益化に必要ですが、配置と頻度には配慮が必要です。“広告よりもコンテンツが主役”という原則を守ることで、ユーザーもGoogleも安心して評価できるサイトになります。
まとめ:Googleが好むのは「信頼できる人の言葉」
Googleに嫌われるページの多くは、共通して「ユーザーを軽視している」点にあります。
SEOのテクニックは時代とともに変化しますが、Googleの理念は変わりません。検索エンジンは常に、「ユーザーにとって最も有益なページを上位に届けること」を目指しています。つまり、Google対策とは、Googleを“だます”ことではなく、“理解されやすくする”ことです。
あなたの体験や専門知識を自分の言葉で伝え、読み手に安心感と信頼を与える。それが結果的にGoogleに評価される最良の方法です。
ページを改善する際は、「検索エンジン」ではなく「人間の読者」を中心に考えること。
その積み重ねが、長期的に愛されるホームページを育て、Googleからの信頼を取り戻す第一歩になるのです。
このコラムを書いた人

さぽたん
ホームページに関するお困りごと、
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください!